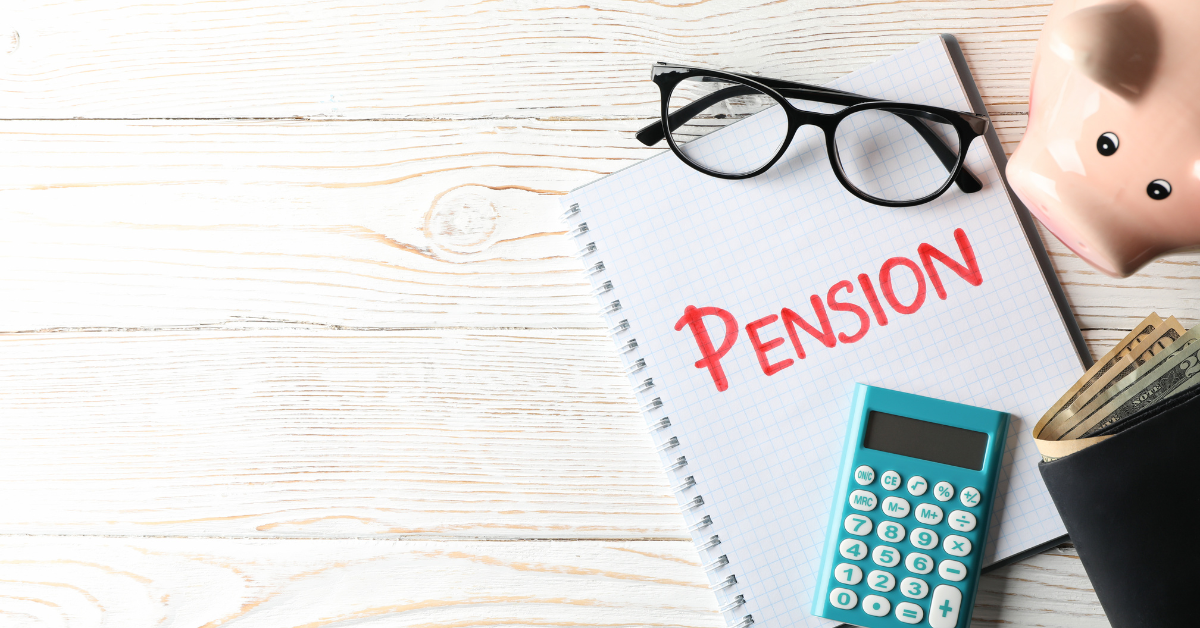要約記事:https://financial-field.com/pension/entry-221654
要約
- 設定:夫が毎月年金で15万円を受給しており、妻はその夫に生計を維持されていた。夫が亡くなった場合、妻は遺族年金をどれくらい受け取れるかをシミュレーション。令和5年度(2023年)基準で試算。
- 遺族年金の種類:遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があるが、このケースでは主に 遺族厚生年金 が該当する可能性が高い。
- 受給要件:
- 夫が公的年金(厚生年金・基礎年金)を受けており、老齢厚生年金を含めていることが想定される。
- 遺族厚生年金を受けるには、被保険者期間(保険料を納めた期間、免除期間、合算対象期間を含めて)25年以上あること。
- 子どもが “18歳になる年度の3月31日まで” の子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害のある子がいる妻なら、遺族基礎年金も併給される可能性。
- 金額の試算: 状況内容夫の年金額月 15万円夫の老齢基礎年金を除く老齢厚生年金部分約 8万3,750円/月妻がもらえる遺族厚生年金その厚生年金部分の 4分の3 → 約 6万2,813円/月もし妻が中高齢寡婦(40〜65歳未満)であれば「中高齢寡婦加算」が上乗せされる(年間59万6,300円) → 年間合計で約 135万56円、月にすると約 11万2,505円 程度。妻が65歳以上で老齢基礎年金満額を受給できる場合、遺族厚生年金と合わせて月約 12万9,063円 程度になる見込み。
- 手続き:自動受給ではなく、年金事務所等で「決定請求」の手続きが必要。戸籍謄本、住民票、基礎年金番号を証明する書類など、状況に応じて準備すべき書類がある。
- 結論:ケースによるが、夫が月15万円年金を受給していた場合、妻が遺族年金・加算・基礎年金等を合わせると、月に12万円前後の年金収入が見込めるというシミュレーション。
誤り・誤りの可能性がある箇所/注意点
以下は記事内で「誤り」あるいは「誤解を招く可能性」がある点、また注意すべき前提条件です。
- 「夫が年金月15万円」という前提
- 記事は「夫が年金を月15万円もらっていた」という前提を置いており、この金額が「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」の合計であることが想定されています。だが、実際にはどのくらいがどちらの年金か、被保険期間がどれくらいか等で大きく変わる。もし夫の厚生年金部分が少なければ遺族年金も小さくなる。
- 「25年以上の被保険者期間」の仮定
- 夫に被保険(保険料納付・免除・合算対象)期間25年以上があることを前提にしており、これは多くの場合満たすが、場合によっては満たしていないこともありうる。もし25年未満なら遺族厚生年金を受けられない。
- 中高齢寡婦加算の対象年齢・条件
- 妻が40〜65歳未満であることが前提。だが、もし妻がこの範囲外であればこの加算はつかない。加えて、加算金額や支給期間は法令改正等で変わる可能性あり。
- 老齢基礎年金満額受給の仮定
- 妻が65歳以上で、基礎年金を「満額」で受給できることを仮定している。だが、満額を受け取れるかどうかは過去の納付状況などに依る。
- 妻自身の老齢厚生年金との関係の説明
- 記事は、妻自身が老齢厚生年金を受給できる場合、「老齢厚生年金相当額」が遺族厚生年金で停止されることを示唆しているが、これはやや簡略化しており、具体的には「代行返上」「停止制度」など、複雑な仕組みや条件が関与する。誤解を招く表現も含む可能性がある。
- シミュレーション額の四捨五入・目安性
- 試算の値はおおよその目安で、「約○○円」という表現。実際に遺族年金を受け取る際は個人の年金加入履歴、納付状況、家族構成、その他法制度の改定などで変動する。
- 法令・制度改正の可能性
- 試算は「令和5年度のもの」と明記されているが、それ以降に制度が変わる可能性があるため「最新情報を確認する必要がある」。
読者がこの記事を読むことで得られること
この記事を読むことで、以下のような知識や理解が得られます。
- 遺族年金の仕組みが分かる
遺族基礎年金・遺族厚生年金の違い、どちらが対象となるか、どのような条件が必要かなど、遺族年金の基本構造が理解できる。 - 具体的な金額の目安を把握できる
夫が15万円の年金を受けていた場合、妻がどれくらいの遺族年金を受け取れるかを具体的な数字で見せており、自分の場合との比較や見込みを立てやすい。 - 手続き・実務上の注意点が分かる
受給のための請求手続き、必要書類、受給要件など、「行動する際に知っておきたいこと」が整理されている。 - 制度上のリスク・変動要因に気付く
記事中に「個別事情によって結果が異なる」「手続きが必要」「条件を満たしていないと受給できない場合がある」などの注意書きがあるため、自分の場合にも同じシミュレーションが当てはまらない可能性を認識できる。 - 老後の生活設計の参考材料になる
遺族年金を含めた年金収入がどうなるかを前もって把握することで、万一の場合の収支計画や保険、貯蓄などの準備を考える材料になる。