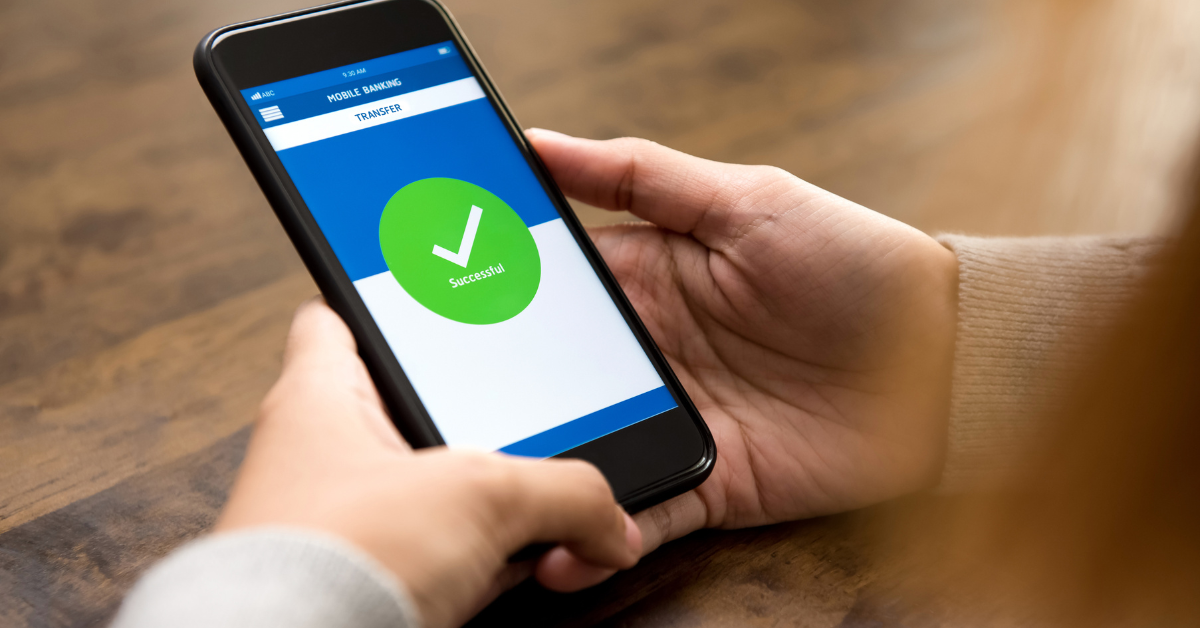要約記事:https://financial-field.com/pension/entry-325992
要約
- 「年金生活者支援給付金」という制度があり、年金受給額が一定の基準を下回る人向けに支払われる追加給付金のこと。2019年10月にスタート。
- 典型的なケースとして、「月6万円」の年金受給者に、支給日にもう一つ(たとえば約5,000円)の振込があるように見えることがあるが、それは誤支給ではなくこの給付金が別途振り込まれているため。年金本体の振込と給付金の振込は同じ日・口座だが“別に記録される”ので、通帳で2件表示される。
- 給付金を受けるための条件は主に3つ。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること。
- 同一世帯の全員が市町村民税が非課税であること。
- 前年の年金収入+その他の所得の合計が 77万8900円以下であること。
- 所得が 77万8900円を少し上回る場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金という制度が適用され、給付金額が調整されるケースあり。
- 給付額の計算方法の概要も出ていて、「保険料を納付した月数に応じた額」+「保険料免除を受けた月数に応じた額」の合計で月額が決まる。たとえば保険料を480月(40年)全て納めていれば給付金月額が「5310円」になるという試算例がある。
- 支給日は年金本体と同じ日に、老齢基礎年金の振込日(偶数月中旬)に前月分がまとめて振り込まれる。振込口座は同じ。ただし別々の振込扱いのため通帳に「老齢年金」と「給付金」の2件の振込が記録される。
- 給付を受けるためには「認定請求手続き」が必要。条件に当てはまる人は忘れず申請を。
誤り・誤解・注意すべき可能性のある箇所
いくつか確認や注意が必要な点がある。
- 所得基準の細かさ・最新情報
記事は「前年の年金収入+その他の所得の合計が 77万8900円以下」という基準を挙げているが、この種の制度は法律改正や物価・税制の変更などで基準が変わる可能性がある。記事の公開時点(2024年9月)ではおそらく正しいが、将来においてはこの数値が変わっていることがあるので最新の厚生労働省や日本年金機構の情報を確認すべき。 - 給付額計算の前提条件
給付額の試算例(保険料納付480月、免除月数など)には、「保険料の納付月と免除月」がすべて典型的に扱われるという前提がある。人によって免除や未納月数がある、または特例がある場合、計算が異なる。さらに、保険料の免除割合によって免除月数の扱いが異なると記事内でも触れているが、全ての人に当てはまるとは限らない。 - 「別の振込=誤支給ではない」という一般論の適用範囲
記事では、「別の振込記録がある=給付金の振込であって誤支給ではないケースがある」と説明している。これは多くの場合正しいが、必ずしもすべての場合において異なる振込が給付金であるとは限らない。たとえば、他の手当や控除の調整、過誤が起きているケースもありうるので、心配な場合は年金機構等に確認することが望ましい。 - 「補足的老齢年金生活者支援給付金」の説明
所得基準を少し上回る人に対する調整制度として「補足的老齢年金生活者支援給付金」が挙げられているが、この制度がどのように適用されるかの具体的計算式・比率など詳細は記事では簡略化されており、実際の給付額が期待した通りになるとは限らない。 - 記事の更新日・修正履歴の有無
記事末尾に「※ 2024/9/24 記事を一部、修正いたしました。」とある。 つまり、過去に誤りや古い情報があって修正された可能性があるので、修正内容も確認したほうがいい。
読者はこの記事から何を得られるか
この記事を読むことで、読者は以下のような知見やメリットを得ることができる。
- 年金生活者支援給付金という制度の存在と目的
年金だけでは収入が少ない人に対して、公的に支援がある制度があることを知ることができる。 - 給付を受けるための条件が何か
年齢、所得、税の非課税条件など、自分自身がその制度の対象になるかどうかを判断するための基準がわかる。 - 給付額の目安の計算方法
保険料納付/免除月数によってどれくらい給付金がもらえるかの具体例があるので、自分の状況に当てはめて考えるヒントになる。 - 通帳の振込が「2件ある」からといって誤支給とは限らないこと
複数の振込履歴が見えても、それが制度上の正しい振込であるケースがあることがわかり、過剰に不安になる必要はない。 - 手続きの必要性を認識
給付を受けるには「認定請求」という手続きが必要で、忘れないようにすること、申請をしなければ受け取れないことも理解できる。