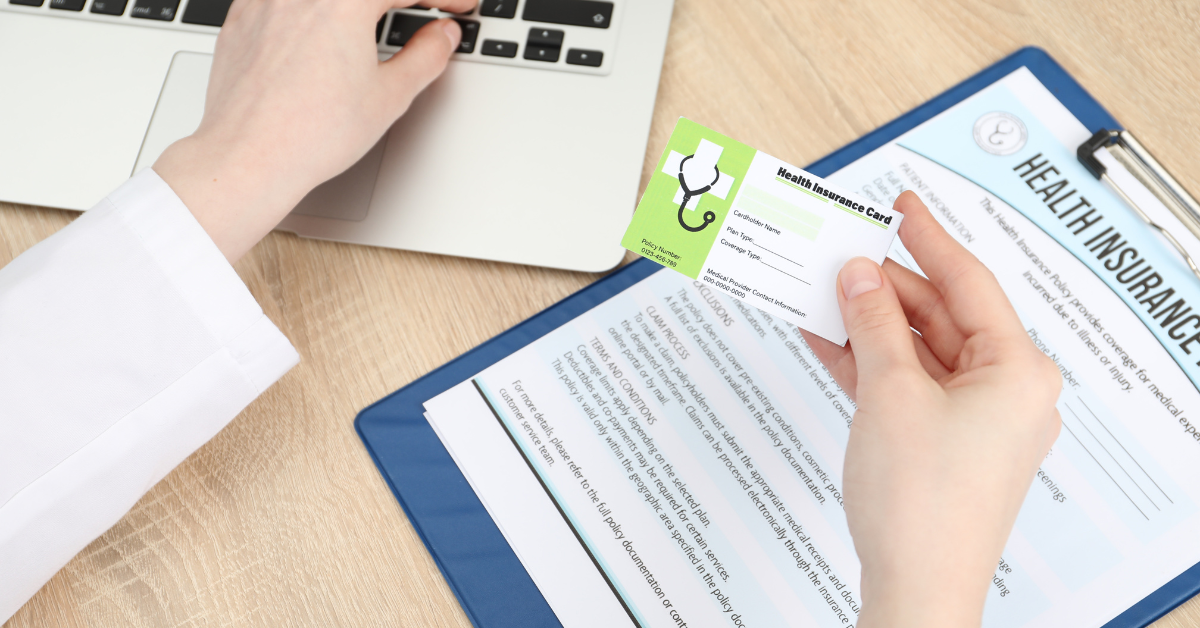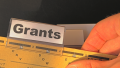要約記事:https://financial-field.com/income/entry-316932
要約
この記事は、「健康保険証の番号(保険者番号、特に最初の2桁=法別番号)によって、勤務先(大企業/中小企業など)が推測でき、収入の目安になるのではないか、という噂」について解説を試みるものです。
主な内容の流れは以下
- 健康保険証の番号とは何か
健康保険証には「保険者番号」という番号が記載されており、その中の最初の2桁(法別番号)が、どの保険組織・保険形態かを示す。
たとえば、法別番号「01」は全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する中小企業従業員、法別番号「06」は組合管掌健康保険(一般に大企業など)など。
(国民健康保険の場合は法別番号の概念はない、という説明もある) - 法別番号の意味・分類
記事では、代表的な法別番号と、それに対応する勤務先タイプを以下ようにまとめている(例):
- 01:協会けんぽ(中小企業従業員)
- 06:組合管掌健康保険(大企業従業員)
- 31:国家公務員共済組合
- 32:地方公務員共済組合
- 34:公立学校共済・私立学校共済 など - 大企業と中小企業の平均賃金比較
厚生労働省の統計(賃金構造基本統計、毎月勤労統計)をもとに、企業規模別に月給・賞与を比較。
例として、大企業(従業員1000人以上)では月額給与平均 34万6,000 円、他規模と比べて高め、といった数字を挙げている。
また賞与を含めた年収換算も示し、「大企業の方が賞与込みの年収でも有利になる可能性が高い」と主張。 - 結論・注意
法別番号「06」だからと言って必ずしも高収入というわけではないが、「どのような会社・組織か(大企業か中小企業か、公務員かどうかなど)」をおおまかに推測する材料にはなり得る、という見方を示して記事を締めくくっている。
誤り・誤りの可能性・注意すべき点
この記事自体は一般向け説明として比較的まとまっていますが、以下の点には注意が必要、あるいは誤り・誤認の可能性があります。
| 指摘内容 | 解説・リスク |
|---|---|
| 法別番号だけで収入を判断するのは拡大解釈 | 記事も「高収入と断言できない」と書いているが、読み手が「06=高収入」という単純な図式に飛びつく可能性がある。実際には企業の業種、職種、勤続年数、地域、役職など多くの要因が収入を左右する。 |
| 法別番号の割り当て・実態の変化 | 法別番号の体系自体や組合管掌制度・共済制度の適用範囲は、制度変更や企業の健康保険の選択・変更によって変わる可能性がある。古い事例や例外は存在する。 |
| 統計数値の引用・解釈 | 記事が引用している「令和5年賃金構造基本統計」や「毎月勤労統計」などは正しい一次情報だが、それら平均値・中央値は分布の極端値に左右されうる。大企業の平均が高い、というのは確かだが「平均 ≒ 典型値」と結論付けるのは慎重であるべき。 |
| 因果関係の混同 | 記号「06」だから高収入、ではなく「06」の法別番号を持つ会社(大企業等)は、制度上給料も高めという傾向がある場所が多い、という「相関・傾向論」である。ただし個別ケースでは逆もありうる。 |
| 国民健康保険の扱い | 記事中に「国民健康保険は法別番号がない」とする説明があるが、国民健康保険には保険者コードがあるなど実務上の識別番号体系を持っている自治体もあるため、単純化しすぎかもしれない。 |
| 最新データの適用・更新 | 引用データが最新かどうか、また制度改正が反映されているかは記事公開時点でのもの。将来の変更(保険制度改編、健康保険組合の再編など)があると説明が古くなる可能性がある。 |
総じて、読者は「保険証番号だけで年収は決められない。ただし保険証の番号には加入先のヒントがある」という理解を持つべきです。
記事を読むことで読者は何を得られるか
この記事を読むことで、読者は以下のような知見・注意を得られます。
- 健康保険証に記されている「保険者番号(特に法別番号)」には意味があり、それによって保険の管掌主体(協会けんぽ、組合管掌、共済組合など)が分かること
- その保険者番号から「大企業/中小企業/公務員」などのおおまかな勤務先形態を推測できる可能性があること
- 企業規模別の賃金統計データを使って、大企業と中小企業との差異(給与・賞与含めた年収ベースでの傾向)を把握できること
- ただし、制度上の仕組みや統計から得られる「傾向」と、個別の実態(個人の給与)を混同してしまうことへの注意
- 健康保険証の番号を眺めるだけで「収入が分かる」という噂の真偽を、自分で判断できるようになる視点
つまり、保険証番号の意味を知ることで「番号が示す可能性・限界」を理解でき、噂に流されず冷静な目で見るための知識が得られる、という点が主なリターンです。